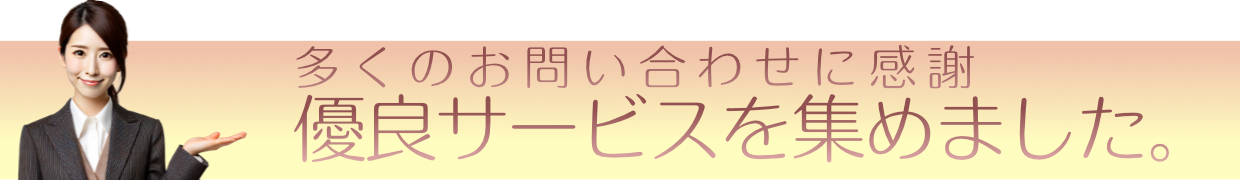更新日:2024年12月2日 | Naoki
起業を考える中で、「税金はいつから支払うのだろう?」と不安を抱える方も多いかもしれません。法人税や住民税、消費税など、起業後に必要な税金は多岐にわたり、それぞれ申告や納付のルールがあります。また、税額控除制度や特別償却など、法人税を軽減する仕組みを活用すれば、事業の資金をより有効に活用することも可能です。
このページでは、税金に関する基本的な知識をわかりやすく解説し、必要な手続きをスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。大切な事業をスタートする第一歩として、ぜひ参考にしてください。

一方で、税金を軽減できる控除制度もあります。例えば、賃上げ促進税制や試験研究費の税額控除、中小企業投資促進税制などを利用すれば、負担を減らしながら資金を有効活用できます。ただし、これらの制度には条件があるため、事前に内容を理解しておくことが大切です。
起業時には覚えることが多く、税金の手続きは煩雑に感じられるかもしれません。しかし、こうした仕組みを把握することで無駄な負担を減らし、やりたい事業に集中できる環境を整えられます。挑戦を恐れず、必要な情報を味方につけることで、一歩ずつ前に進む力になるはずです。
法人税はいつから支払う必要があるのか?

起業後に初めて法人税を支払う時期を知っておくことは、計画的に事業を運営する上でとても重要です。余裕を持って対応するためにも、基礎的な知識をここでしっかり学びましょう。
事業年度が終わった後、いつまでに納税すればよいのか?
会社を設立したら、最初の決算日を自分で決めることができます。そして、決算が終わった後、税金を支払う期限が決まります。この期限を守ることで、安心して事業を進めることができます。例を使ってイメージしやすく説明します。
- 決算月は設立時に自由に決められる
- 決算が終わると2ヶ月以内に申告と納税が必要
- 例)5月が決算月の場合、7月31日までに納める
事業年度終了後、2ヶ月以内に必ず税金の手続きを済ませることが大切です。
納付期限に間に合わないとどんな問題が起きるのか?
税金の支払いが期限を過ぎると、延滞税や延滞金が発生します。この金額は遅延した日数に応じて増えるため、早めの対応が大切です。期限を守ることは、余計な出費を防ぐためにも重要です。
- 延滞税と延滞金は期限を過ぎた場合に発生する追加の支払い
- 遅れた日数が増えると、金額も上がる仕組み
- 一日でも早く支払えば、負担を減らせる
期限を過ぎた場合は、すぐに納税することで負担を最小限に抑えることが大切です。
起業後に法人が支払う税金の種類
起業後には複数の税金を支払う必要があります。それぞれの税金の仕組みを理解しておくことで、無駄な出費を防ぎ、事業を安定させることができます。
法人税とは何か?
法人税は、会社が事業で得た利益に対して支払う国の税金です。売上から経費を引いた金額が課税対象となり、所得に応じて税率が異なります。正しい計算で納税することが重要です。
- 法人税は会社の所得に課税される税金
- 売上(益金)から経費(損金)を引いた金額が対象
- 所得が800万円以下の部分は15%の税率
- 800万円を超える部分は23.2%の税率
売上から経費を引いた所得をもとに法人税を計算し、正確に納めることが大切です。
法人住民税とはどのような税金か?
法人住民税は、会社の所在地や事業所がある地域に納める地方税です。この税金には、「法人税割」と「均等割」という2つの部分があります。それぞれの仕組みを理解して正確に対応することが大切です。
- 法人住民税は地方自治体に支払う税金
- 法人税割は法人税をもとに計算され、利益が多いほど税額が増える
- 均等割は利益に関係なく、資本金や従業員数によって決まる
法人住民税は、利益に応じた「法人税割」と、利益に関係なく支払う「均等割」の2つで構成されています。
法人事業税の仕組みとは?
法人事業税は、会社が得た所得に基づいて課税される地方税です。この税金は、法人の種類や資本金、所得額によって税率が異なります。また、法人税などの中で唯一、経費(損金)として計上できる特性があります。
- 法人事業税は所得に応じて地方自治体に納める税金
- 税率は法人の種類や資本金の大きさで異なる
- 損金算入が認められ、経費として扱える
法人事業税は所得に応じた地方税で、損金算入ができるため経費として計上可能です。
消費税はどう支払うのか?
固定資産税の対象になるものとは?
固定資産税は、会社が所有する土地や建物、製造用機械、パソコンなどに課される税金です。土地や建物は申告不要ですが、設備や備品については自治体への申告が必要な場合があります。これらの税金は経費として計上可能です。
- 固定資産税は土地や建物、設備などに課される税金
- 土地や建物は申告不要で納付書が届く
- 償却資産税は設備や備品にかかり、毎年申告が必要
- 固定資産税と償却資産税は経費として認められる
固定資産税は資産の種類によって申告の必要が異なり、経費として計上可能です。
その他に法人が負担する税金
法人が負担する税金は、所得税の源泉徴収や印紙税など多岐にわたります。これらを正確に処理することが、事業運営をスムーズにする鍵です。
- 源泉所得税は役員報酬や給与から控除し、国に納める税金
- 源泉所得税は毎月概算で計算し、年末調整で精算
- 印紙税は契約書などの課税文書に収入印紙を貼付して納付
法人は給与の源泉徴収や契約書の印紙税を正確に処理する必要があります。
法人が活用できる税金の控除制度

起業後に利用できる控除制度を知っておくことで、税金の負担を軽減し、資金を効率的に活用できます。
税金を減らせる制度とは?
税額控除は、会社が支払う税金を減らす制度です。一定の条件を満たすと、法人税から直接控除されます。中小企業が従業員の給与を上げた場合や、研究開発費を使った場合に利用できる制度が含まれます。
| 制度名 | 概要 | 控除の内容 |
|---|---|---|
| 賃上げ促進税制 | 従業員の給与支給額を増加させた中小企業が、要件を満たすと控除が可能。 | 増加額の一部を法人税から控除 |
| 試験研究費の税額控除制度 | 試験研究費を使った法人が、一定割合を法人税から控除できる制度。 | 試験研究費の一定割合を控除 |
税額控除制度を活用すると、法人税の負担を軽減しながら事業を拡大できます。
中小企業向けの特別税制(特別償却や税額控除)
中小企業投資促進税制は、会社が機械や装置を購入した場合に利用できる制度です。購入した資産をもとに「特別償却」または「特別税額控除」のいずれかを選び、法人税を減らせます。事業内容に合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。
| 制度名 | 概要 | 控除内容 |
|---|---|---|
| 特別償却 | 資産の取得価額の30%を加算して減価償却できる制度。法人税の課税所得を減らす。 | 資産取得価額×30%を償却額に追加 |
| 特別税額控除 | 算出した法人税額から資産取得価額の7%を直接控除できる制度。 | 資産取得価額×7%を法人税から控除 |
中小企業投資促進税制では、特別償却と特別税額控除のどちらかを選んで法人税を減らすことが可能です。
Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。
 度重なる会議でも要点を逃さないAIボイスレコーダーとは?
一番売れているベストセラーを知っています?
度重なる会議でも要点を逃さないAIボイスレコーダーとは?
一番売れているベストセラーを知っています?
まとめ:起業して税金はいつから?法人税と控除について知っておこう
起業を考えるとき、税金について正しく理解しておくことは大切です。法人税やその他の税金は、起業後の事業運営に直接影響を与えるため、スムーズな対応が求められます。法人税は、事業年度が終わった後、2ヶ月以内に申告と納付が必要です。この期限を守ることで、余計なペナルティを避け、安心して事業に集中できます。
また、法人住民税や法人事業税といった地方税も重要です。法人住民税は、利益に基づく法人税割と、利益に関係なく支払う均等割から成り立っています。一方、法人事業税は所得に応じて課税され、経費として計上できる特長があります。これらをしっかり把握することで、適切な納税が可能になります。
さらに、消費税については、基準期間や特定期間の課税売上高が一定額を超える場合に納税義務が発生します。設立後すぐに支払いが求められるケースもあるため、事前に確認しておくことが重要です。固定資産税や償却資産税も事業用の資産を所有する法人には欠かせない税金ですので、申告の有無を含め、適切に対応しましょう。
税金の負担を軽減するためには、控除制度を活用することも効果的です。例えば、中小企業向けの賃上げ促進税制や試験研究費の税額控除、中小企業投資促進税制などがあります。これらの制度は、条件を満たせば法人税の負担を軽くする手助けとなります。
起業には多くの準備が必要ですが、税金について正確な知識を持つことで、事業をよりスムーズに進めることができます。適切な対応を心がけることで、やりたい仕事に集中し、夢を形にしていくことができます。